母の実家には大きなクルミの木がありました。すぐ目の前は崖で、下はゆるやかな坂道です。高台の林地が終わり、開けた扇状地がはじまる。その境目が母の実家でした。
ある年の夏まだ小学生だった母は、そのクルミの木の下でじれったい思いを胸に立ちつくしていました。
荒削りの砂利道をたくさんの自転車がガタガタ、キイキイ騒がしくつぎつぎと下っていきます。男たちは砂ぼこりを残し、猛スピードで先を急いでいました。
彼らがめざしたのは近隣で随一の港町。今日は街が最も賑わう花火大会です。
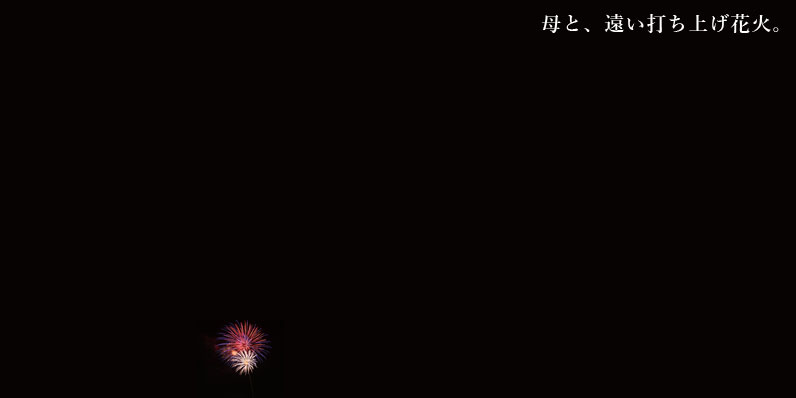
母は近所のお姉ちゃんたちの仲間に入れてもらえず一人おいてけぼりになっていました。何が悔しいって「○○ちゃんはまだ小さいから」というヒソヒソ話が耳に入ったことでした。4人姉妹の長女で負けん気が強かった母は、花火が見に行けないことより、こんな大切な日にぼうっと家にいることがお間抜けに思え、そんな屈辱はぜったい嫌だったのです。
*
「連れてってばっ!」
母親に、祖母に、はじめは懇願していたはずですが、どうにもラチがあかず、ついには怒り出し、泣きわめく始末。もううるさくてお手上げになった祖母は近所の本家の義甥に「ちょっとばかり連れて行ってくれないか」と頼みに行くはめとなりました。
母の癇癪は毎度のことで、ある日熱を出したのをいいことに、前年の村祭りに本家でごちそうになった「かんぴょう巻き」が食べたいと駄々をこね、ついにはせしめるという前科もあります。頑固な長女に家の者はほとほと手を焼いていたようです。
*
さて、そうしたわけで涙で目を腫らした母のもとに“チャリの王子”がやってきました。祖母の義甥は20代半ばの青年で、母とは仲良し。学校帰りに本家に寄ると何かと声をかけてくれるやさしいお兄ちゃんでした。
教えられたとおり後輪の軸に両足を掛け、サドルの下を両手でしっかりつかんだ母を荷台に乗せ、お兄ちゃんは慎重に漕ぎ出しました。やがて自転車はクルミの木の下で眺めた男たちのように風を切って進みます。母はもうそれだけで満足でした。だって花火をまだ見ていなくても「見に行く」ことが実現したのだから。
*
平坦な道を十数分ほど走ったところでお兄ちゃんは自転車を止めました。遠くからドーン、ドーンという音が響いて聴こえます。もう昼の熱波は去り、辺りはひんやりとした空気に包まれていました。
「ほら」とお兄ちゃんが前方を指さします。
荷台から腰を浮かせ、目をやると、そこには菊の小花のような色とりどりの花火が薄暮の田んぼの向こうに浮かんでは消えていました。
*
後日、母は親から小言を聞かされます。
「なあ。お前のせいだ。本家のお兄ちゃんは笑われたってよ。『いい年をして嫁をもらうどころか小さい女の子と花火に行った』ってな」
*
もう80年も前の出来事です。年老いた母は「へへへっ」と笑うと、お兄ちゃんの姿を思い浮かべるかのように炬燵の上の宙に目をやりました。


